※この考察は、NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」のネタバレを含みます。
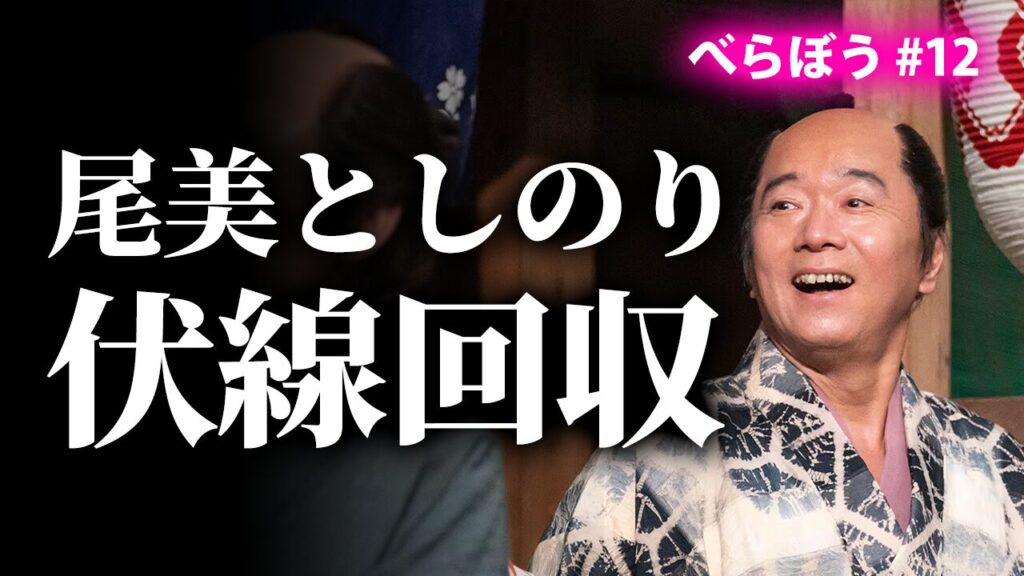
SNSでたびたび話題になっていた、「尾美としのりさんが出演している?!」という情報。
第12話ではついに、尾美としのりさんが平沢常富役で登場することとなりました。
やっと画面の中央に登場したので嬉しいですね!笑
今日はその尾美さんが演じている平沢常富とはどのような人物なのか?
わかりやすく解説していきたいと思います!
⇩ちなみに、他にもべらぼうに関する記事を書いていますので、興味のある方はぜひ読んでいただけると嬉しいです⇩
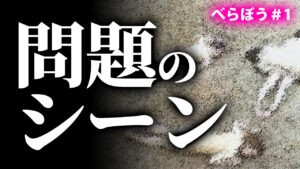
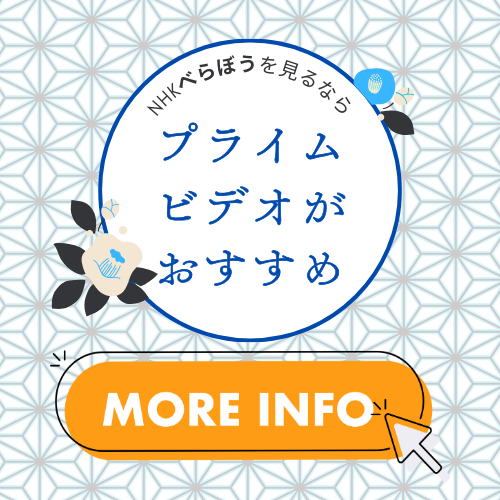
平沢常富は江戸幕府と他藩をつなぐ外交官

平沢常富は1735年、西村平六久義(にしむら へいろくひさよし)の三男として誕生しました。
14歳の時に、母方の親戚である平沢家へ養子入り。
平沢家は秋田県の久保田藩でつかえていました。
久保田藩の「江戸留守居役 筆頭」として働き、
年収は現代の金銭に換算すると、およそ1,200万円くらいだったそうです。
 おーいぬ
おーいぬなかなかの高収入ね!
ちなみに「江戸留守居役」とは、幕府や他藩との連絡調整を行う外交官のような役割のこと。
その筆頭を勤めたのですから、平沢常富はかなり優秀だったのではないでしょうか。


一方で、覆面クリエイターとしても活躍


平沢は、芸術の才能も持ち合わせていました。
役所仕事に支障が出ないよう、名前を変えて活動していたといいます。
以下は平沢のペンネームです。
朋誠堂喜三二:戯作者として。べらぼうではこの名で登場しました。
手柄岡持(てがらの おかもち)、楽貧王(らくひんおう):狂歌師として。
亀山人(きさんじん):青本作家として。
道陀楼麻阿(どうだろう?まぁ):滑稽本作家として。
雨後庵月成(うごあん げっせい)、朝東亭(ちょうとうてい):俳人として。
平角(ひらかく、へいかく):通称。通称とは成人した男性が諱(生前の実名)を直接呼ばぬようにつけた名前で、公文書などにも多く記載
知足(ちそく):字。字(あざな)とは中国大陸の習慣で、成人男性の諱(生前の実名)に代えて呼ぶ名前。
愛洲(あいす):号。祖先の苗字から。
平荷(へいか):隠居号。



わしに負けないくらいペンネームを持っているな…
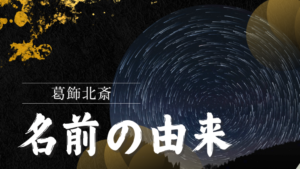
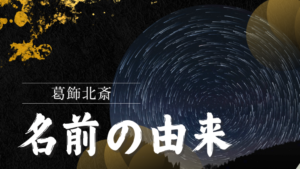
外交官たちの情報交換の場となったのが吉原
そんな江戸留守居役たちの情報交換の場となったのが、吉原でした。
朋誠堂喜三二は「宝暦の色男」と自称し、吉原に通い詰めていたそうです。



だから尾美さんがちょくちょく画面に登場していたのね!
吉原通いをするうちに、蔦屋重三郎とも交流を持つようになり、洒落本「娼妃地理記(しょうひちりき)」を刊行。
蔦屋重三郎にとって、朋誠堂喜三二は最大の協力者でもありました。
そして、吉原についての知見を活かして執筆した「当世風俗通(とうせいふうぞくつう)」を出版し大ヒット!
また、「親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)」という黄表紙も刊行。
こちらも大ヒットし、江戸の売れっ子作家となりました。



恋川春町が挿絵を描いたよ!
しかしその後、寺田心くん演じる松平定信による寛政の改革が発令。
出版業界にも大きな影響を与えました。
1790年に出版統制令が出され、出版には制限がかかりました。
朋誠堂喜三二が1788年に執筆した「文武二道万石通」が、松平定信の寛政の改革を風刺しているとして問題視され、定信から怒られました。
そしてこの書物を最後に黄表紙から引退してしまったのです。
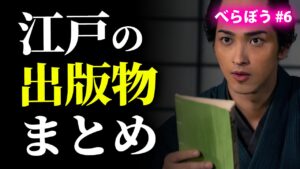
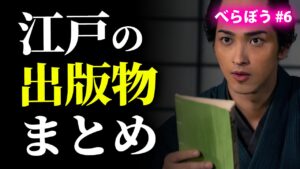
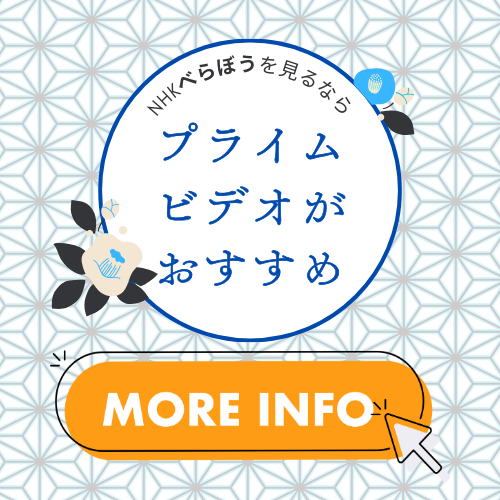
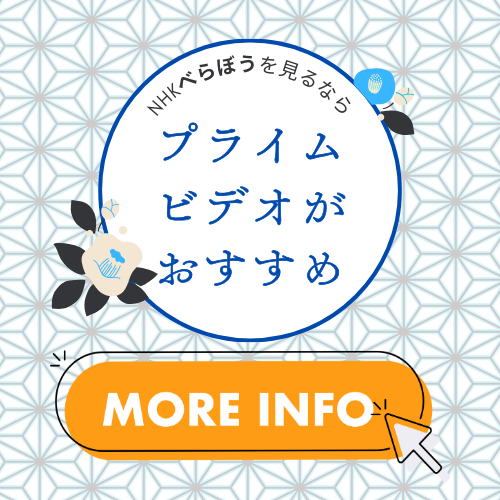
その後は狂言師として活躍
その後は「手柄岡持」(てがらのおかもち)という名前で、田沼時代から力を入れていた狂歌に集中するようになりました。
そして1813年(文化10年)に亡くなりました。
気になる方は公式SNSもチェックしてみてください!
今後も、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の情報や考察を発信していきますので、気になる方はぜひチェックしてくださると嬉しいです!
私たちは化政文化にインスパイアされた現代的音楽を制作しています。
ぜひ聞いてくださると嬉しいです。
本サイトでは、アフィリエイト広告を利用、またはプロモーション記事が含まれている場合があります




