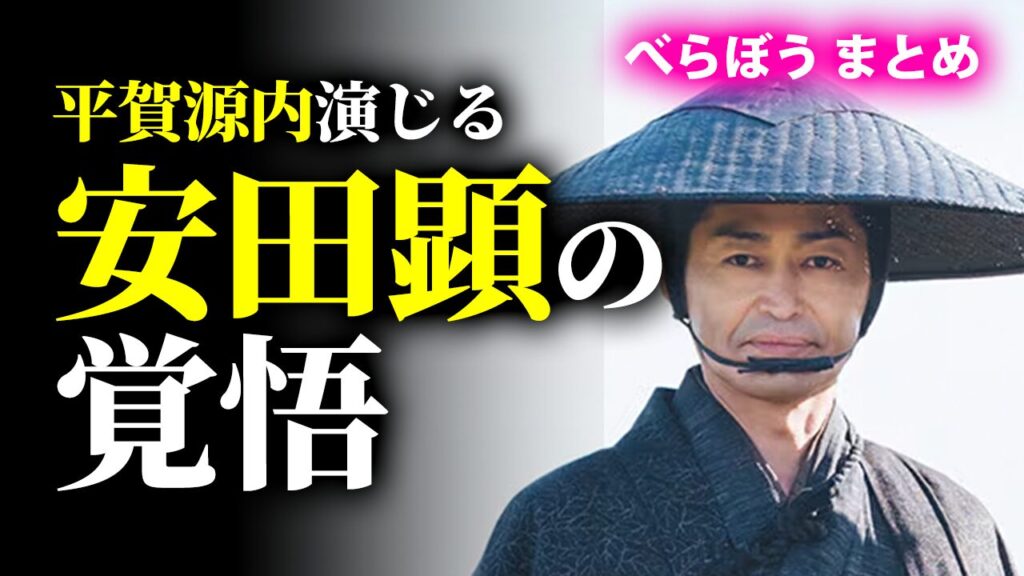
※この考察は、NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」のネタバレを含みます。
 ほくさいぬ
ほくさいぬ源内先生は多彩で明るくておもしろい人だなあ〜



歴史の中でも名前だけ聞いてサッと通り過ぎてしまうけど、べらぼうを見ていると源内先生の魅力がたくさん伝わってくるよね



最近はドラマ内での存在感も一層増してきたし、今回は平賀源内と安田顕さんについて徹底的に深掘りしていくよ!
⇩ちなみに、他にも大河ドラマべらぼうに関する記事を書いていますので、興味のある方はぜひ読んでいただけると嬉しいです⇩
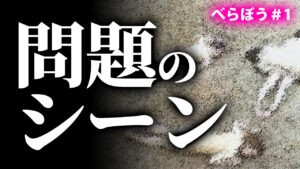
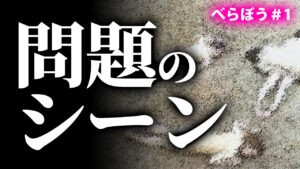
平賀源内とは?





そもそも平賀源内ってどんな人?
平賀源内は、江戸の発明家、薬剤師、はたまた人気浄瑠璃作家、西洋画や源内焼を広めたプロデューサーなど…
簡単に言うと超多才の有名人でした。
特に発明の分野では、エレキテル(日本で初めて復元された電気機器)、燃えない布・火浣布、量程器(万歩計)、磁針器等多くの発明をしたという記録が残っています。



江戸のレオナルドダヴィンチってとこかしら
ちなみに、「土用丑の日に鰻を食べようキャンペーン」を始めたのも平賀源内です。
当時は人気のなかった鰻を高級料理に仕立て上げてしまったのですから、源内の商才には驚かされます。
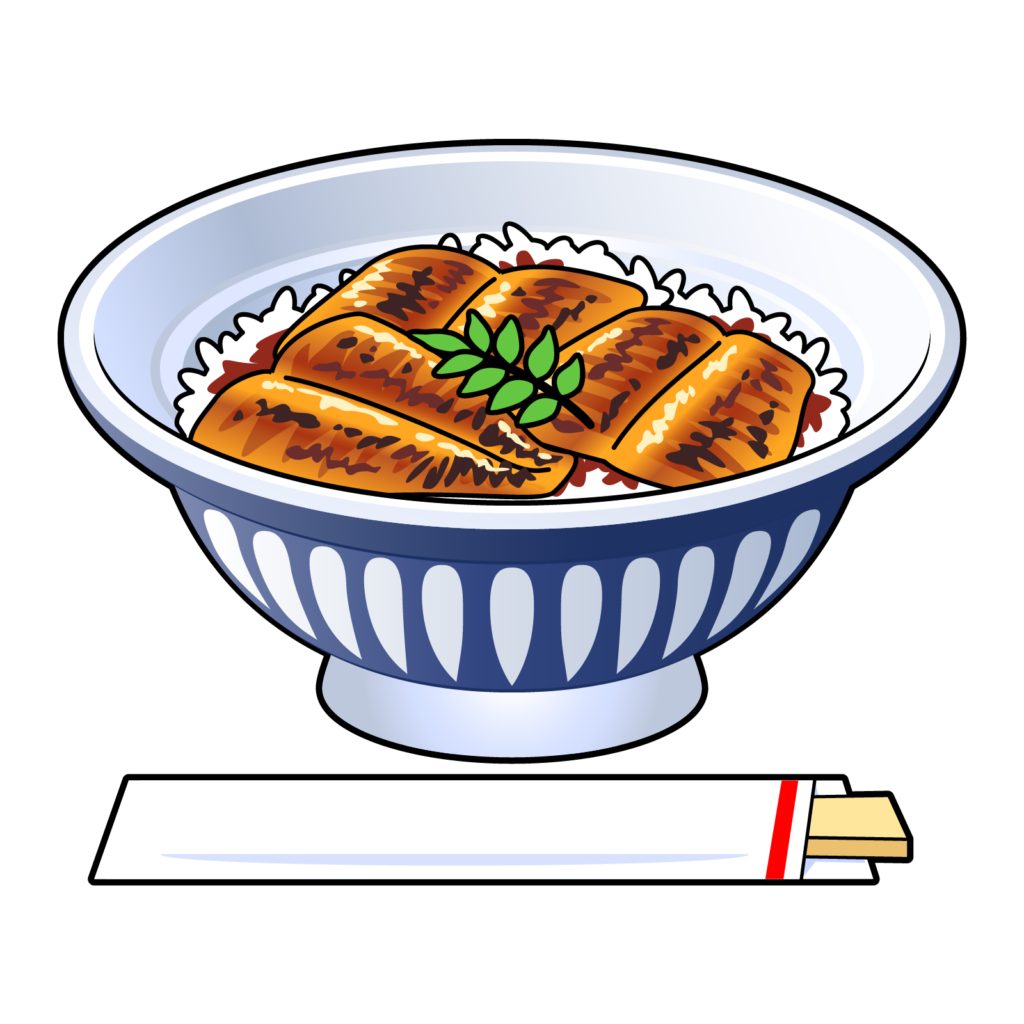
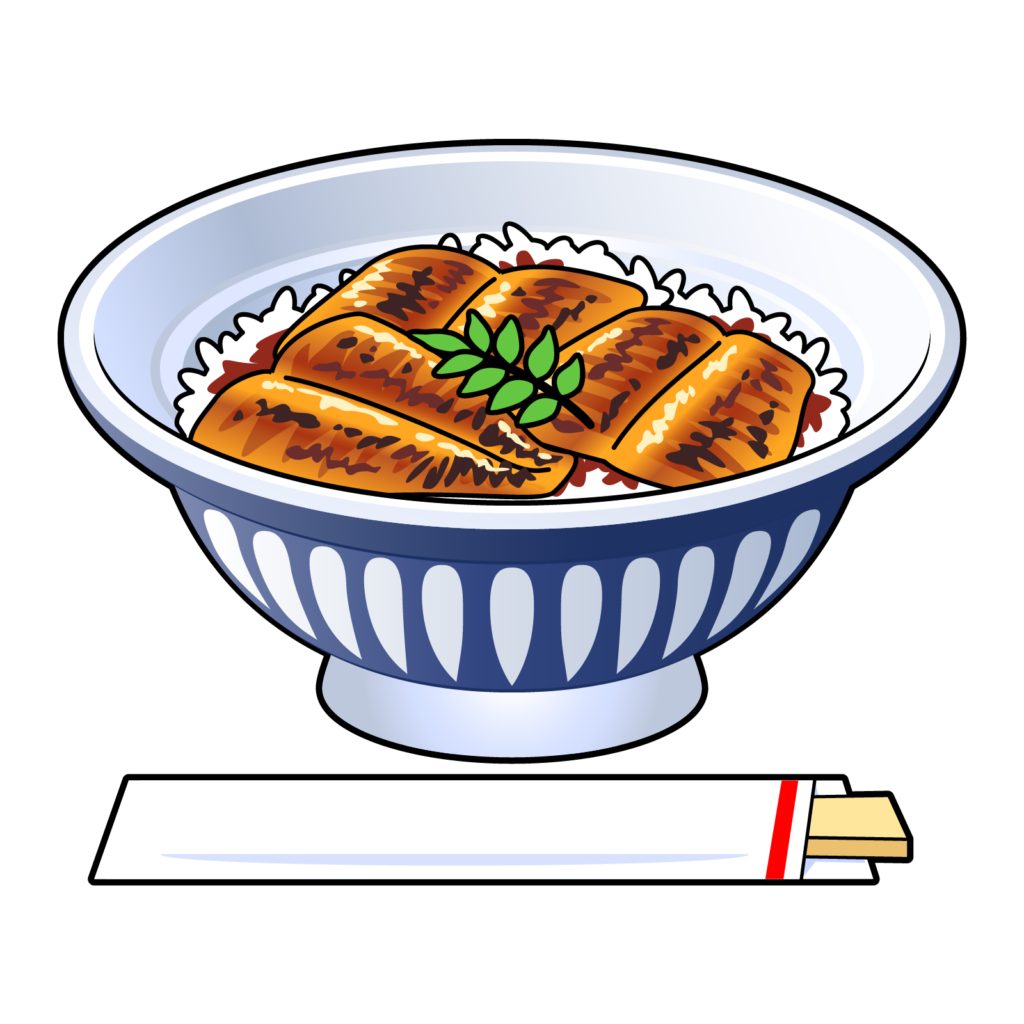
また、源内は男色でも有名でした。
美少年・美青年好きで、歌舞伎役者(女形)の二代目瀬川菊之丞との思い出はべらぼう第二話でも描かれていますね。
瀬川の変装と重なるように幻となって登場した、女形の人気歌舞伎役者・二代目・瀬川菊之丞と恋仲であることは、江戸市中でも有名でした。
『根南志具佐(ねなしぐさ)』という男同士の恋愛を描いた戯作も出版し、その中にも菊之丞が出てきます。
また、源内は一生、独身でした。
吉原については詳しくなかったようですが、若衆が体を売る町には詳しかったという説もあります。
その証拠に源内は『男色細見』という男娼がいる店のガイドブックを作っています。



吉原細見の男バージョン?!
蔦重もビックリだわ!



意外にも、日本では平安時代末期から明治時代初期まで約800年間、男色は背徳的な行為ではなかったから、源内先生も差別に遭うことはなかっただろうね。



同性愛者だからこそ、人と違った視点のアイデアが生まれたのかもしれないね!


べらぼう 蔦重と平賀源内の出会い
第二話で、蔦重は吉原を立て直すための策を考えます。
江戸で人気の「漱石香」(そうせきこう)という歯磨き粉の宣伝文句をヒントに、年に2回発行される「吉原細見」の「序」の部分を平賀源内に書いてもらい話題性を上げようとしました。



「序」というのは、今でいう本の「帯」みたいな役割をはたしていたよ。
松葉屋に案内された平賀源内は、早速、花魁の「瀬川」を指名します。
しかし現在、瀬川の名を継ぐ者はいませんでした。
源内は男色であったため、蔦重をからかっていたのですね。
その後、序を書く条件として、蔦屋重三郎に花魁の格好をするように迫ります。
蔦重が覚悟を決めかけた瞬間、男装した花の井(後の瀬川)が現れたのです。
花の井は、源内が探している「瀬川」とは、花魁の「瀬川」ではなく、亡くなった歌舞伎の女形「瀬川菊之丞」(せがわきくのじょう)だと察し、瀬川菊之丞を彷彿とさせる男装をして、源内と一夜を過ごそうと考えたのです。
その花の井の姿に菊之丞を重ね、平賀は涙が溢れてくるのでした。



むかし、源内先生は瀬川菊之丞と恋仲だったよ
しかし、さすが江戸の男。
そこで涙を流すことはなく、花の井に「夜風にあたってくる」と告げて去り、吉原を徘徊しながら蔦重からの依頼文を練り上げるのでした。
ちなみに源内が書いた「序」の文章は以下です。
女衒、女を見るには法あり。
一に目、二に鼻筋、三に口、四にはえぎわ、次いで肌は、歯は、となるそうで、吉原は女をそりゃ念入りに選びます。
とは言え、牙あるものは角なく、柳の緑には花なく、知恵のあるは醜く、美しいのに馬鹿あり。静かな者は張りがなく、賑やかな者はおきゃんだ。
何もかも揃った女なんて、まあいない。
それどころか、とんでもねえのもいやがんだ。
骨太に毛むくじゃら、猪首、獅子鼻、棚尻の虫食栗。
ところがよ、引け四つ木戸の閉まる頃、これがみな誰かのいい人ってな。
摩訶不思議。世間ってなあ、まぁ広い。繁盛、繁盛、嗚呼御江戸。
([べらぼう]第2話より抜粋)
この文章は、平賀源内は本名ではなく人形浄瑠璃の脚本でも使用していた「福内鬼外」(ふくちきがい)のペンネームで執筆されました。
女郎達を厳しく評価つつも、懸命に生きる女郎達に対する尊敬の念を感じる文章になっています。
吉原に通う人々、まだ訪れたことがない人達にも届くような言葉に、誰もが心惹かれたことでしょう。
安田顕が源内の故郷・讃岐(香川)を巡る


平賀源内を熱演した安田顕さんが、源内の故郷・さぬき志度を巡るバラエティが放送されました。
源内が故郷に残した思いや源内マインド=「創意工夫の精神」を引き継ぐ老若男女に遭遇。
地元の小学校では、源内が授業や校歌にまで登場!
源内の子孫・平賀家7代目当主との対談なども見れるとても貴重な番組でした。



発明の息吹は子どもたちにも脈々と受け継がれていたね。
番組内で語った平賀源内を演じる上で大切にしていること



べらぼうの源内がひょうきんな人柄だから、ついつい安田顕さんもそんな性格に感じてしまうけど、実際はとても真面目な方よね
番組内の安田顕さんが語った言葉で印象的だったお話。
「平賀源内は最終的に「ああいうふうに亡くなってしまった」けど、僕は彼の人生を肯定してあげたい。
それは僕が源内の人生を演じるものとして、全てを受け入れたいから。
※という旨のお話をしていました。完全な文字起こしではありません。
「ああいう風な亡くなり方」とは一体どんな最期だったのでしょうか?
実は、源内は殺人事件を起こし獄中死しているのです。



えー!?
予想外すぎる!
エレキテルの発明から3年後、源内はある大名屋敷の工事を任されました。
しかし宴席のあと、源内は酔っぱらってしまい、設計図を盗まれたと勘違いして大工達を殺傷してしまったのです。



べらぼうでは、弥七がエレキテルの設計図を盗んで質の悪い模造品が出回り、源内先生の評判は一気に悪くなってしまったよね。
投獄された源内は獄中で破傷風を患い、51歳で亡くなりました。



友人だった杉田玄白は、源内のお墓の隣に碑を残しているんだ。
その碑には、以下のような言葉が残されています。
「ああ非常の人、非常の事を好み、行いはこれ非常、何ぞ非常に死ぬる」
(人と違い、好みも行いも常識を越えていたあなたは、死に方まで常識と違うのですか)



人を殺めてしまったとはいえ、きっとたくさんの人に慕われていたんだろうね
安田さんが役者として大切にしているポリシーを感じることができてとても良い映像だったと感じました。



その人の人生を全肯定してあげるのって、もしかしたら役者以外できないかもしれないよね…



改めて、とても難しいお仕事だと思ったわ


気になる方は公式SNSもチェックしてみてください!
今後も、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の情報や考察を発信していきますので、気になる方はぜひチェックしてくださると嬉しいです!
私たちは化政文化にインスパイアされた現代的音楽を制作しています。
ぜひ聞いてくださると嬉しいです。
本サイトでは、アフィリエイト広告を利用、またはプロモーション記事が含まれている場合があります




